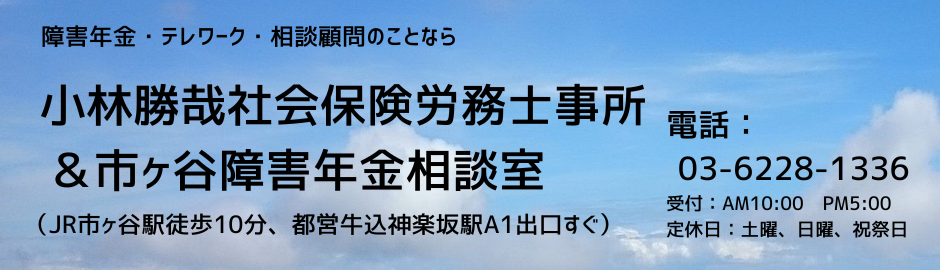■ワークエンゲージメントのその先に
■ワークエンゲージメントのその先に
(働き方ブログ)
みなさま、こんにちは!
この数年間で働き方改革への様々な取り組みが行われていますが、社員一人一人のいきいきとした笑顔があってこそ、企業の発展もあります。
これまで健康経営という視点からは、社員のダメージ(アブセンティーズム)や健康が万全でないことからくる生産性の低下(プレゼンティーズム)を予防することが着目されてきました。
しかし、最近では「弱みを支える」ことから「強みを伸ばす」ことへ軸足を移して健康経営を行っていくことにより、不調面への対策だけでなく、前向きな取組みで職場のチームとしての活性化を目指しておられる企業も増えてきました。
現在、「ワーク・エンゲイジメント」という新しいメンタルヘルス対策の概念が国内外で注目されています。これは、仕事に誇りを持ち、エネルギーを注ぎ、仕事から活力を得ていきいきしている状態のことです。いきいき働くことで、人間の持つ強みやパフォーマンスが上がり、組織面、経営面での成長につながります。

厚生労働省では、ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等に力を入れています。
ストレスチェックは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促すことで、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させ、検査結果を集団的に分析して職場環境の改善につなげ、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
このストレスチェック結果の集団的分析に使われる、新職業性ストレス簡易調査票にも「ワーク・エンゲイジメント」についての項目が追加されています。
厚生労働省の研究では、仕事の要求度-資源モデル(JD-Rモデル)とワーク・エンゲイジメントについて、強い相関関係があることがわかっています。つまり、仕事上で社員がコントロールできる資源を増やし、かつ個人の仕事上の心理的な希望を増やすような、職場ミーティングや社員教育について少し改善を図ることで、社員の「ワーク・エンゲイジメント」が大きく向上し、企業の業績も向上するといえます。
仕事の要求度-資源モデル(JD-Rモデル)からワーク・エンゲイジメントの向上を通じた労働生産性の向上に寄与する健康増進手法についての主要な職種・業種ごとのガイドラインやマニュアルも、整備されています。
皆様の職場でも、法定のストレスチェックを実施することから一歩進めて、社員の「ワーク・エンゲイジメント」が大きく向上し、企業の業績も向上する取り組みを始めてみませんか?
当事務所では、健康経営に関するご相談にも対応しております。ご一緒に、社員の笑顔溢れる職場を作ってまいりましょう。
2021年2月4日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表 小林勝哉
(参考)
・厚生労働省 令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-
仕事の要求度-資源モデル(JD-Rモデル)とワーク・エンゲイジメントについて
(北里大学 一般教育部人間科学教育センター教授 島津明人氏)
・基調講演「健康でいきいきと働くために:ワーク・エンゲイジメントに注目した職場と個人の活性化」
(厚生労働省 平成30年度 職場のメンタルヘルスシンポジウム、北里大学 一般教育部人間科学教育センター教授 島津明人氏)
・厚生労働省 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施者向け関連情報
・厚生労働省 ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
・健康指標として見るワーク・エンゲイジメント (株式会社iCARE)